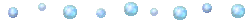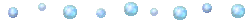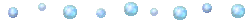Gift(ありがとうございます!)
□『おくりもの。』(小説)
2ページ/4ページ
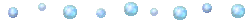
セバスチャンは、そう言いきった。
普段のシエルなら、こういう時は決まって怒気を露わにする。
少しでも執事が命令に背くような態度を見せると必ずそうする筈なのに、しかし今日の彼は何も言わず、悲しそうな顔をして俯いてしまった。
何も言わなくなってしまった主人の隣に、セバスチャンは並んで座った。
「けれど・・・そうですね、坊ちゃんがきちんと理由をお話し下されば、全く話は変わって来るのですが」
「・・・理由も何も、折角こっちが寛いでいるのに、そんな堅苦しい恰好で周りをうろつかれるのが目障りなだけだ」
「今までもお休みはありましたが、今まで一度もそのような事を仰ったこと無かったのに?」
「急に気が変わったんだ」
「私がそれで納得するとでもお思いですか、坊ちゃん」
「・・・言わせるのか?」
「はい、是非伺いたいです」
「分かっているんだろう、僕が考えそうなことくらい」
「さあ? 悪魔と言えど、人の心の中まで読むことは出来ませんから。」
「調子のいい時だけとぼけられるんだから、悪魔も便利なものだな」
隣に座るセバスチャンのシャツの袖元に軽く触れると、シエルはゆっくりと言葉を紡いだ。
「折角、お前と、こんなふうにいられるのに」
「はい」
「お前は、いつも、その格好だろう」
「ええ、これがファントムハイヴ家執事の服装ですから」
「だから、それが、嫌だったんだ」
「坊ちゃん・・・」
「自分たちが、執事と主人だと延々言い聞かされているようで、嫌だった」
ゆっくりと、セバスチャンの腕がシエルを自分に引き寄せる。
そしてそれは、何の抵抗もなく受け入れられる。
「・・・主人と執事、ですよ。私たちは、これからもそう有り続ける。貴方がそう望んだからこそ、私はこういう形で傍にいるのです」
「分かっている。それでも、今はそれを、少しだけ邪魔だと思った」
白く細い指が、男の糊のきいたシャツの袖口をぎゅっと握りしめる。
「腑抜けたと思うか。僕のことを」
俯いたまま、シエルはそう問うた。
その肩が、少し、震えたように見えた。
セバスチャンはシエルを体ごと抱き締めると、いつもよりも幾段はっきりとした口調で、ゆっくりと告げる。
「・・・ええ、そうですね。我が主はすっかり柔弱に成り下がったものだと、以前の私ならそう思ったでしょうね。嘲笑う気にもなったでしょうが」
次の言葉に身構えるシエルの唇は、その時にはすでにセバスチャンのそれに塞がれていた。
激しいものではなく、体温を伝え合う様な、穏やかな瞬間。
シエルも、自然と目を閉じてそれを受け入れた。
セバスチャンはその交わりを解くと、またすぐにお互いの唇が触れ合うか触れ合わないかの距離のまま、
「けれどひどく嬉しくて、堪らなく貴方にキスをしたくなってしまったのですが、どうしましょうか」
そう、こっそりと囁いた。
「・・・もうしてるだろうが、馬鹿め」
真っ赤になった顔を隠しながら、シエルは今言える精一杯の強がりを口にした。
きっと返って来るのは嘲りだろうと腹を括っていたシエルにとって、それはとても嬉しくて、安堵出来ることだった。