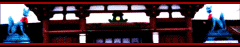
1ページ/36ページ
夜の帳が降りた、京都郊外の山の中……
古びた窓から淡い橙の光を零すのは、時代の移ろいの中で取り残されたような木造の民家だった。
その民家の居間――
暖を取るための囲炉裏の小さな炎が揺れる中……
まだ若い夫婦は言葉も、呼吸さえも忘れてしまったように硬直していた。
二人の見開いた視線の先に揺らめくのは、巨大な狐の形をした漆黒の影……
その影は夫婦の方を向いたかと思うと、風が森を揺らすような声で問いかけた。
『お前達、娘に光を与えて欲しいか』
その言葉を聞いて、二人はハッと目を見合わせる。
狐の言う光とは恐らく、七歳になった二人の娘・小春の視力のことだろう。
小春は先天的に、原因不明の障害で光を知らずに生まれてきた。
医者にも治せないと知った二人は、前々から信仰していた伏見の社の稲荷神に、
"何とか治療法を見つける事が出来るように"
と祈り続けてきたのである。